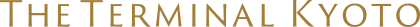展示・イベント
- ホーム
- 展示・イベント
展示・イベント
スケジュール
最新情報
-
2025年7月17日(木) イベント
- 祇園祭【巡行】
- 前祭りでは23基の鉾が京都市を巡行します。
鉾は祇園囃子の音色と共に、細い道もギシギシ・ドスンドスンと音をたてながら進み、間近くで見ると迫力があります。
角を曲がる「辻回し」も見どころです!
-
2025年7月14日(~7月15日(火) イベント
- 祇園祭【奉納舞台「天岩戸のカミあそび」】【童舞「こどもカミあそび」】
- 天照大神(あまてらすおおみかみ)・伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・手力雄尊(たぢからのみこと)の三柱の御神体人形を頂く岩戸山に因み、
日本神話の名場面「天岩戸の神楽ーかみあそびー」を、舞と篠笛で披露。
15日は子供たちが、篠笛、祇園祭と岩戸山の縁起歌、童舞を披露します!
観覧無料。
-
2025年7月13日(日) イベント
- 祇園祭【曳き初め】
- 3日間にわたり組み立てられる山鉾。17日の巡行に向け、山鉾が安全に動くのかを試します。
数トンある山鉾を地域の人たちが引っ張ります。祇園祭最初の盛り上がりです。
皆様も盛り上げにお越しください。
-
2025年7月11日(金)~7月13日(日) イベント
- 祇園祭【鉾建て】
- 釘を使わずに縄を縛って組み立てていく伝統技法。
鉾に装飾物が着飾れば、その美しい技術は目隠しされるので、是非この期間に受け継がれる職人技をご覧下さいませ。
-
2025年7月1日(火)~7月7日(月) イベント 開催中
- 祇園祭【弐階囃子】
- 京町家2階から風情溢れるお囃子が聴こえてまいります。
お時間は19:30~21:30頃の予定です。
-
2025年5月17日(土)~6月1日(日) 展示
- 修復の練習
- 「オールマイノリティプロジェクト」は発達障害者をはじめとするマイノリティが、社会的孤立・孤独に陥らないフェアな社会の実現を目指す研究開発プロジェクトです。
当プロジェクト2025年度シンポジウム「修復の練習:当事者と非当事者の溝を埋める」に連動し、築92年の京町家建築The Terminal KYOTOにて、他者とのコミュニケーションや関係性の再構築に着目した展覧会を開催します。本展では、「壊さない」ことよりもむしろ、「壊れたものを修復する」ことの大切さに心を寄せる現代美術家の作品を展示し、分かり合えなさを共に超えていくための視点を提供します。
-
2025年5月3日(土) イベント
- 室礼展トークイベント
- テーマは「室礼展とは何か?」私とあなたの室礼展!
室礼展が11年続けてきたことを振り返り、原点を見直し、これから先の室礼展について、展示作家数人による座談会。
-
2025年4月19日(土) イベント
- 室礼展ギャラリーツアー
- 展示作家数人による作品解説
-
2025年4月12日(土)~5月11日(日) 展示
- 室礼 SHITSURAI -Offerings Ⅺ
- 室礼とは何か
場には場の個性がある
作家がそこに作品を室礼る
場とモノは互いに響き新たな場を作る
それはその場のヒトと響き合う
小さな響は新たなモノに場にヒトに響いていく
ひとつひとつは小さなものだ
小さなものが響き合い世界に広がる
室礼展は11回目迎えます。
会場であるターミナルは大きな町家で土間や縁側、中庭、防空壕、、、様々な場があります。
作家は作品を展示するのではなく室礼する
原点に戻り室礼とは何かをもう一度問直します。
そこにはバラバラになりそうな世界をひとつに紡ぐヒントがある。
-
2025年3月1日(土)~3月23日(日) 展示
- カイロスとクロノスの狭間 或いは存在と痕跡の考察(後期)
- カイロスとクロノスとは、ギリシャ哲学における2つの時間概念である。
ギリシャ時代に考察されたこの二つの時間概念は、クロノスが物理的に計測可能な量的時間であることに対し、カイロスは主体的に認識され刻まれる瞬間的時間と定義されていた。
近代になり、相対性理論と量子力学、宇宙物理学などの発展により時間の概念が大きく変遷した。
我々が存在する世界の概念が多くの転換期を迎えている現代、クロノス的不可逆の時間の流れの中で、各アーティストがカイロス的時間を丹念に刻み続けて表現した痕跡としての作品を、1000年の歴史を持つ古都京都の中で存在してきたThe Terminal KYOTOの空間に展開する。
-
2025年2月8日(土)~2月23日(日) 展示
- カイロスとクロノスの狭間 或いは存在と痕跡の考察(前期)
- カイロスとクロノスとは、ギリシャ哲学における2つの時間概念である。
ギリシャ時代に考察されたこの二つの時間概念は、クロノスが物理的に計測可能な量的時間であることに対し、カイロスは主体的に認識され刻まれる瞬間的時間と定義されていた。
近代になり、相対性理論と量子力学、宇宙物理学などの発展により時間の概念が大きく変遷した。
我々が存在する世界の概念が多くの転換期を迎えている現代、クロノス的不可逆の時間の流れの中で、各アーティストがカイロス的時間を丹念に刻み続けて表現した痕跡としての作品を、1000年の歴史を持つ古都京都の中で存在してきたThe Terminal KYOTOの空間に展開する。
-
2024年12月7日(土)~12月22日(日) 展示
- 春望 ーshunbouー
- ロックダウンにより社会が一変したとき、私たちは何を感じたのか。
不確かな世界で、山河の中に小さな自分を見つめ直す——。
方巍(絵画 )、UMA (パフォーマンス )、宙宙 (インスタレーション )、谷川美音 (漆芸 )、山口遼太郎 (陶芸 )による展覧会。
当時上海に住んでいた本展キュレーターの金澤韻によるエッセイも展示。
-
2024年11月8日(金)~11月10日(日) 展示イベント
- 窯と土三周年記念企画展「千紫万紅」
- 2021年にオープンした窯と土は、来月いよいよ無事三周年を迎えようとしています。
つきましては三周年を記念して、京都「The Terminal KYOTO」にて企画展を開催いたします。
本年は唐津や備前など日本陶にルーツを持つ写真掲載作家の茶陶作品を中心に、当店取り扱い作家の最新作を出展いたします。
茶碗や茶入、酒器などに加え、小服茶碗や振出等、茶箱用の作品も展示販売。さらに金沢の仕覆作家、多田けい子さんの茶箱を5点、特別展示いたします。
まさに千紫万紅、三周年記念に相応しい内容の三日間。作家の在廊もございますので、是非この機会にThe Terminal KYOTOにお立ち寄りください
-
2024年10月16日(水)~11月4日(月) 展示
- ヴィラ九条山での工芸レジデンス10周年
- 2014年から、ヴィラ九条山は主要メセナのベタンクールシュエーラー財団の支援を受け、レジデンスプログラムに工芸部門を受け入れるようになりました。
この10周年を記念した本展示では、イザベル・オリヴィエと珠寳によるキュレーションのもと、ヴィラ九条山で滞在してきた工芸レジデントのこれまでの経験、作品やリサーチを紹介します。
-
2024年10月11日(金)~10月13日(日) 展示イベント
- 光象展
- 日本各地で活躍されている陶磁、彫刻、紙、京金網、ガラス、絵画、友禅、紬織、彩色、いけばな、造園、表具など、様々な分野の作家が一同に会し、豊かな表現を展開する《光象展》を開催いたします。
展示と同時に販売も行いますので、ぜひご高覧ください。
また今回、去年逝去された光象展メンバー・陣内久紹(友禅)追悼展を同時開催いたします。